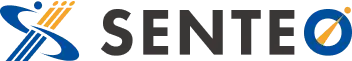ストレスチェック義務化へ!50人未満の企業が今すぐ始めるべき対応策とは?

目次
2025年5月、ついに「従業員50人未満の事業場」にもストレスチェックの実施が義務化される法改正が可決しました。これまで努力義務にとどまっていた小規模事業場に対しても、メンタルヘルス対策が“法的義務”となる時代が始まろうとしています。施行は「公布後3年以内」とされていますが、余裕がある今のうちに準備を始めるかどうかで、将来の対応コストや職場環境に大きな差が生まれます。
「うちは人数も少ないし、形式的に済ませればいいだろう」と軽く考えていると、従業員の信頼を損なうリスクや、制度違反による企業イメージの低下を招きかねません。
本記事では、法改正のポイントを整理するとともに、50人未満の企業が“今”から取り組むべき対応策と、後れを取らないための実践ステップを分かりやすく解説します。制度に振り回されるのではなく、メンタルヘルス対策を「組織強化のチャンス」に変えていきましょう。
第1章:法改正の内容とストレスチェック義務の全体像
2025年5月8日、「労働安全衛生法および作業環境測定法の一部を改正する法律案」が国会で可決しました。この中で、従業員50人未満の事業場にもストレスチェックの実施を義務化する内容が明記され、企業規模を問わずメンタルヘルス対策が求められる時代が本格化しています。
改正法では、「ストレスチェックの実施義務」を小規模事業場にも拡大する形となり、施行は公布後3年以内に政令で定める日とされています。これは、企業に準備期間を与えつつ、確実に全事業場へ制度を浸透させる狙いがあると考えられます。
義務化の背景には何があるのか?
近年、職場のメンタルヘルス不調による休職・離職が深刻化しており、特に人手不足に悩む中小企業では、一人の不調が組織全体に与える影響が大きくなっています。厚生労働省はこれらの問題に対応するため、予防的なメンタルヘルス対策の徹底を強く打ち出しており、今回の法改正もその一環です。
また、労働環境や人間関係の問題を放置していると、ハラスメントや労災、早期離職、採用難などさまざまなリスクへと波及しかねません。企業が受け身ではなく、「従業員の心の健康に責任を持つ姿勢」を示すことが、今後ますます重要になるでしょう。
小規模企業に求められる義務内容は?
法改正により、50人未満の企業も以下のような対応が求められるようになります:
年1回のストレスチェック実施(標準的な質問票を用いる)
実施者は医師または保健師等であること
従業員本人への結果通知
一定基準を超えた従業員に対する医師面接の機会提供
プライバシー保護の徹底と、上司や他部門への情報漏洩の防止
第2章:50人未満の企業が受ける影響と見落としがちな課題
「人事も労務も経理も、全部一人でやってる」。そんな企業にとって、今回のストレスチェック義務化は、決して小さな負担ではありません。

2025年の法改正によって、従業員が50人未満の事業場でも、年1回のストレスチェック実施が“法律で義務付けられる”時代がやってきます。対象になるのは、社員が10名でも20名でも例外ではありません。義務となる以上、やらなかった場合には「法令違反」として扱われる可能性も出てきます。
とはいえ、「人手も予算も限られたうちの会社で、いったいどう対応すればいいのか…」というのが本音ではないでしょうか。ここでは、50人未満の企業だからこそ直面しやすい課題と、その回避策を整理していきます。
1. 担当者がいない、または兼任で手が回らない
中小企業では、人事専任の担当者がいないケースも少なくありません。総務担当者が帳簿をつけながら、片手間で制度対応をしなければならないこともあります。こうした状況では、ストレスチェックの法的ルールや手順を調べるだけでも一苦労です。
そのため、「手間なく、法令に沿って、安心して任せられる外部の委託先」を見つけることが、最初のハードルになります。
2. 産業医がいない/専門家とのつながりがない
ストレスチェックの実施には、医師や保健師などの専門職の関与が必要です。しかし、50人未満の企業の多くは、そもそも産業医と契約していないため、「誰に相談すればいいか分からない」と悩みがちです。
この場合、ストレスチェック専門の実施機関や外部サービスを活用することで、制度に必要な実施者・運営体制をまとめて確保することができます。
3. 実施して終わり、にしないために
ありがちな失敗が、「やったことにして終わり」にしてしまうケースです。形だけ整えて、結果を活用しなければ、社員の信頼を失うことになりかねません。
特に注意したいのが集団分析の“放置”です。結果を見ても対策を取らなければ、社員から「どうせ何も変わらない」と思われてしまいます。
実施後は以下のポイントに注目して改善に活かすことが大切です:
高ストレス者の割合や部署の傾向を確認
業務量、人間関係、職場環境の課題を見える化
小さくても具体的な改善アクションを打つ
こうした対応が、「この会社はちゃんと社員の声を聴いてくれている」という信頼につながります。
4. プライバシーへの配慮が命綱
小さな組織では、「誰が何を答えたか」が想像できてしまうこともあります。そのため、匿名性の確保や結果の取り扱いについて、従業員に明確に伝えることが不可欠です。
回答内容が上司に見られることはない
結果は個別通知され、本人の同意なしに共有されない
集団分析は個人を特定できない範囲で活用される
こうした前提を説明した上で実施することが、社員の安心感につながり、正直な回答を引き出すことにもつながります。
第3章:事前に動いた企業だからこそ得られるメリットとは?

ストレスチェックの義務化が正式に決まった今、まだ時間に余裕があるからこそ、早めに動いた企業が得られるメリットは決して小さくありません。ここでは、実際の導入に先んじて取り組んでおくことで、どのような効果やプラスの変化が期待できるのかを解説します。
1. 離職の予防と定着率の向上
ストレスチェックを通じて、従業員の不調や不満の兆候に早期に気づければ、メンタル不調による休職や離職を未然に防ぐことができます。
小規模な組織では、ひとりが抜ける影響が大きいため、「ひとりを守ること=組織を守ること」に直結します。
2. 職場環境の改善に活用できる
ストレスチェックでは、個人結果だけでなく、部署ごとの傾向を分析できる「集団分析」も可能です。これを活かすことで、特定の部署に偏るストレス要因や、人間関係・業務量の偏りといった課題を“数値で可視化”できます。
感覚では気づけない職場の問題点をデータで把握し、小さな改善を積み重ねることで、働きやすさを実感できる組織風土づくりが進みます。
3. 社員の信頼を得られる
「きちんと社員の声に耳を傾けようとしている」
その姿勢自体が、社員にとっては安心材料になります。匿名性やプライバシー配慮を徹底した上で制度を運用することで、会社に対する信頼や安心感が育まれ、結果としてエンゲージメントの向上にもつながります。
4. 採用・対外的な印象にもプラス
近年、求職者は給与や条件だけでなく、「安心して働けるか」「会社は社員を大切にしているか」といった点にも注目しています。
ストレスチェック制度の導入や職場改善への取り組みは、企業の姿勢を伝える重要なメッセージにもなり、採用活動においてもプラスに働く可能性があります。
5. 本格施行時の「慌てない準備」ができる
いざ制度が完全施行された際、「体制が整っていない」「対応できる人がいない」と慌てて対応を始める企業も少なくないでしょう。今のうちに仕組みや委託先、社内の役割分担を整えておけば、施行後もスムーズに運用が始められます。
このように、義務化を“負担”として捉えるのではなく、信頼・改善・採用・定着といった企業力の底上げに活かす視点が、今後ますます求められていくでしょう。
第4章:今すぐ取り組むべきストレスチェック対応ステップ
ストレスチェック義務化の施行は「公布後3年以内」とされていますが、実際の準備には時間がかかります。特に人手の限られた50人未満の企業では、「早めに着手しておくこと」が後の混乱を防ぐ最大のポイントです。ここでは、義務化に備えて今からできる4つのステップをご紹介します。
ステップ1:社内の実施体制を整える
まずは、社内でストレスチェックを担当する責任者を決めましょう。総務や人事の担当者が中心になることが多いですが、実施者は医師・保健師などの専門職である必要があります。そのため、社内体制と合わせて、外部との連携先も検討しておくことが重要です。
併せて、従業員への実施通知文や運用ルール(実施規程)も準備しておくと、制度化された際にスムーズに対応できます。
ステップ2:外部サービスを比較・検討する
自社単独で実施するのが難しい場合は、外部の専門サービスに委託するのが現実的な選択肢です。費用感は事業所の規模によりますが、1回あたり数万円程度から対応可能なサービスも増えてきました。
選定時は以下のポイントを確認しましょう:
法令遵守の体制が整っているか
高ストレス者対応や医師面談手配までサポートしているか
実施後の「集団分析」や「職場改善提案」まで含まれるか
ステップ3:社員に制度の意義を丁寧に伝える
制度が義務化されても、従業員の協力なしには成り立ちません。特に小規模事業場では、「上司に内容が伝わるのでは」と不安に感じる社員も多いため、匿名性の確保やプライバシー保護について事前にしっかり説明することが大切です。
「やらされる」制度ではなく、「安心して働ける環境をつくる取り組み」として伝えることで、制度の信頼性と実効性が高まります。
ステップ4:結果を活かした改善サイクルを準備
ストレスチェックは「実施すること」ではなく「活用すること」が目的です。集団分析の結果を放置せず、課題の可視化→改善施策の立案→次年度に向けた振り返りというPDCAサイクルを設けることが、企業としての評価や信頼にもつながります。
外部サービスを利用する場合は、こうした職場改善支援まで含まれているかを確認しましょう。
義務化されたその日から準備を始めるのでは、間に合いません。今この段階から一歩ずつ対応を進めていくことが、社員の安心感と企業の信頼構築に直結します。
まとめ:義務化はピンチではなくチャンス
ストレスチェックの義務化は、「小規模企業にとって負担が大きい制度」ではなく、職場環境を見直す絶好の機会です。
少人数だからこそ、改善の効果が目に見えやすく、離職防止や信頼構築といった成果に直結しやすいのが実情です。
「義務だから仕方なくやる」のではなく、「社員が安心して働ける職場づくりの第一歩」として捉えることで、制度は大きな力になります。
制度の内容や対応方法に不安がある方は、外部の専門サービスの力を借りて無理なく取り組むことも一つの選択肢です。
弊社では、50人未満の企業様向けに、ストレスチェックの実施支援や制度設計のご相談を無料で承っております。
まずはお気軽に資料をダウンロードのうえ、貴社の状況に合わせた導入準備をご検討ください。
👉【無料資料ダウンロードはこちら】