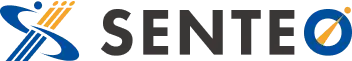ストレスチェックは義務!企業が対応すべき実施要件と導入フローを1から解説

目次
1. なぜストレスチェックは義務なのか?背景と目的を知る
働く人の心の健康を守る仕組みとして、ストレスチェックの実施は企業にとって欠かせない取り組みです。
この制度は、2015年12月に労働安全衛生法の改正によって導入され、現在は「従業員50人以上」の事業場で実施が義務づけられています。
ストレスチェック義務化の背景
メンタルヘルス不調による休職・離職の増加
働く世代の自殺問題
心身の不調によって業務効率が落ちる「プレゼンティーイズム」への対策
これらの課題に対し、「こころの不調を未然に防ぐ」一次予防策としてストレスチェック制度が生まれました。
不調になってからの対応ではなく、早期発見と環境改善につなげることが、この制度の大きな目的です。
今は「50人以上」が義務。でも50人未満も無関係ではない
現在、義務化の対象は常時使用する労働者が50人以上の事業場です。
一方で、50人未満の小規模事業場は「努力義務」とされています。
しかし、厚生労働省は今後、50人未満への義務化も検討する方針を公表しています(2023年「今後の労働安全衛生対策のあり方に関する検討会」より)。
すでに自治体や業界団体によっては、独自に50人未満企業へ実施を推奨しているケースも増えています。
「まだ対象外だから…」と後回しにしていませんか?
義務化を待つのではなく、今から取り組むことには大きなメリットがあります。
小規模企業こそ取り組むべき理由
少人数の職場ほど一人ひとりの不調が業務に直結しやすい
「話しづらい」「相談できない」環境が生まれやすい
離職や人間関係のトラブルが経営インパクトにつながりやすい
法改正に備え、スムーズに導入できる体制を早めに整えられる
中小企業でも、ストレスチェックを上手に活用すれば、職場環境改善のきっかけになります。
結果として、離職防止や人材定着にもつながり、採用面での企業イメージ向上にも効果的です。
「義務だからやる」だけではもったいない
ストレスチェックの目的は、単なる法律対応ではありません。
重要なのは、
従業員が自分のストレス状態に気づくこと
必要なサポートを早めに届けること
職場として課題を把握し、改善につなげること
こうした取り組みを続けることが、
健康経営の推進や働きやすい職場づくりにつながります。
制度を上手に活用して、不調を防ぎ、安心して働ける環境を整えていきましょう。
2. 企業が押さえるべきストレスチェック実施要件と守るべきルール
ストレスチェックは、実施すればそれで終わりというものではありません。
法律で決められた**「やるべきこと」と「守るべきルール」**があります。
これらを正しく理解し、適切に実施することが企業には求められています。
対象となる事業場と労働者
まず、実施が義務となるのは、常時使用する労働者が50人以上の事業場です。
ここでいう「労働者」には、正社員だけでなく、契約社員やパート、アルバイトなども含まれます。
ただし、短期間の勤務や一時的な雇用の場合はカウントしない場合もあり、判断に迷う際は専門家への確認が必要です。
実施者になれる人の条件
ストレスチェックは、誰でも実施できるわけではありません。
一定の資格を持った専門職が「実施者」として行う必要があります。
具体的には、次のような職種が対象です。
医師
保健師
看護師(一定の要件あり)
精神保健福祉士(一定の要件あり)

企業の人事担当者が質問票を配布するだけでは、法的に正しい実施とは認められません。
必ず、適切な実施者を立てて対応する必要があります。
実施頻度と基本の流れ
ストレスチェックの実施は、年に1回以上が義務付けられています。
その基本的な手順は以下の通りです。
- 実施方針の決定(衛生委員会での審議など)
- 従業員への説明と実施への同意取得
- 質問票の配布と回答回収(紙またはWEB)
- 結果を本人へ通知
- 高ストレス者に対して面接指導を案内
- 企業は必要に応じて職場環境の改善に取り組む
特に注意が必要なのは、回答は従業員の自由意思であることです。
「全員必ず提出」と強制することはできません。
守るべきルールと企業の注意点
ストレスチェックの運用には、法律で定められた守るべきルールがあります。
特に以下の点には注意が必要です。
結果は本人に直接通知すること
本人の同意がなければ、企業が個人の結果を把握してはいけない
高ストレス者への面接指導は、あくまで本人の希望に基づいて実施する
不利益取り扱いの禁止(結果を理由に配置転換、降格、解雇などNG)
実施者や事務従事者による守秘義務の徹底
このルールを守らずに運用した場合、法令違反となるリスクがあります。
さらに、従業員からの信頼を損ない、制度そのものが形骸化してしまう恐れもあります。
正しい手順で、安心できる仕組みづくりを
ストレスチェックは、従業員の心の健康を守るための大切な仕組みです。
ただ義務として実施するだけではなく、安心して受けられる環境を整えることが何よりも重要です。
そのためにも、制度の趣旨とルールをしっかり理解し、正しく運用していきましょう。
3. ストレスチェック導入の流れをわかりやすく解説
ストレスチェックは、ただ実施するだけでは意味がありません。
きちんと準備を整え、正しい手順で実施することが求められます。
ここでは、企業が実際にストレスチェックを導入する際の流れを、ステップごとにわかりやすく解説します。
【STEP1】計画づくりと体制の整備
まず必要なのは、実施計画の策定です。
事業場に衛生委員会がある場合は、実施方法やスケジュールについて審議し、意見を聞いたうえで計画を立てます。
この段階で、実施者(医師、保健師など)や事務従事者(質問票の配布や回収を行う担当者)を決めておくことが大切です。
必要に応じて、外部サービスの利用も検討しましょう。
【STEP2】従業員への説明と同意の取得
次に、ストレスチェックを行うこと、実施の目的、個人情報の取り扱い、結果通知の流れについて、従業員へ十分な説明を行います。
この説明を通じて、チェックを受けるかどうかは本人の自由であること(任意であること)をきちんと伝えることが必要です。
【STEP3】チェックの実施と結果通知
説明と同意を得たら、いよいよ実施に入ります。
厚生労働省が提供する**57項目の質問票(職業性ストレス簡易調査票)**が広く使われていますが、外部委託の場合はカスタマイズされた設問を利用できることもあります。
実施方法は、紙でもWEBでも可能ですが、最近は回答率向上と集計のしやすさからWEB実施を選ぶ企業が増えています。
チェック終了後は、結果を本人に直接通知します。
個人の結果は本人の同意がない限り、企業側が把握することはできません。
【STEP4】高ストレス者へのフォロー
質問票の結果から、一定の基準を超えた「高ストレス者」と判断された場合、
企業はその対象者に医師による面接指導を受ける機会を案内する義務があります。
ただし、受けるかどうかは本人の意思によるもので、強制はできません。
【STEP5】集団分析と職場改善への活用
ストレスチェックは、個人の状態を把握するだけではなく、
職場全体のストレス状況を集団分析することが認められています。
集団分析を行うことで、部署ごとのストレス傾向や、働き方に関する課題が「見える化」され、職場改善につなげるヒントになります。
この流れを守って実施することが、企業としての法的義務を果たすだけでなく、
従業員の信頼を得て、職場環境の改善や健康経営につながる一歩となります。
4. 形骸化させないために。ストレスチェックを本当に役立てるポイント
ストレスチェックを「義務だから仕方なく実施している」という企業は少なくありません。
しかし、形式的に実施するだけでは、本来の目的であるメンタル不調の未然防止にはつながらないのが現実です。
ここでは、ストレスチェックを形骸化させずに、職場改善につなげるためのポイントを解説します。
集団分析結果を「見える化」し、改善に活かす
ストレスチェックで得られる集団分析は、職場環境の課題を把握するための貴重なデータです。
たとえば、「上司の支援が不足している」「仕事量のバランスが悪い」といったストレス要因が部署ごとに浮かび上がります。
これらの結果を社内で共有し、改善に向けたアクションを取らなければ、せっかくの実施が無駄になってしまいます。
分析結果は、経営層や管理職が正しく理解し、改善施策の検討材料として活用しましょう。
高ストレス者へのフォローを確実に行う
個人への通知と面接指導の案内を形だけ行い、その後のフォローが不十分なケースも見受けられます。
高ストレス者への面接指導は、必要に応じて休務や配置転換、働き方の見直しを検討するなど、個別対応までを含めて考えることが重要です。
また、面接指導の内容や改善の進捗は、衛生委員会や経営層と共有し、組織的に対応できる体制を整えておくと安心です。
従業員の安心感を生む仕組みづくり
「どうせ会社にバレる」「面接指導を受けたら評価に響く」といった不安があると、従業員は正直に回答しなくなります。
これでは正しい結果が得られず、対策も打てません。
そのために大切なのが、
個人結果の非開示(本人同意がなければ企業は把握不可)
外部機関への委託などによる匿名性の確保
不利益取り扱いの禁止をしっかり説明すること
安心してチェックを受けられる環境を作ることで、初めて本音の回答が得られます。
継続的に取り組むためのPDCAサイクル
1回実施して終わりではなく、毎年の結果を比較しながら改善を積み重ねていくことが大切です。
ストレスチェックを起点に、
「課題を発見」
「改善策を実行」
「効果を確認」
「次の対策へ活かす」
というPDCAサイクルを回すことで、形骸化せず、職場環境の向上につなげることができます。

義務対応で終わらせず、職場改善のための有効なツールとしてストレスチェックを活用していきましょう。
5. まとめ:義務をきっかけに、働きやすい職場づくりを
ストレスチェックは、単なる「義務対応」で終わらせるのではなく、
働きやすい職場づくりにつなげるための第一歩です。
とくに、メンタル不調は本人だけの問題ではありません。
休職や離職、人間関係の悪化、業務停滞といった形で、組織全体に影響を及ぼします。
だからこそ、制度を形だけのものにせず、正しく運用し、改善へとつなげる姿勢が求められるのです。
また、厚生労働省では今後、50人未満の事業場にも義務化を拡大する方針が示されています。
規模の大小を問わず、早めに仕組みを整えておくことが、社員の安心感にもつながります。
自社での実施や運用に不安がある場合は、外部の専門家に相談するのも有効な選択肢です。
メンタルヘルス対策を「やらされ感」のある義務対応で終わらせず、
経営改善のチャンスとして、前向きに取り組んでいきましょう。
🔗 ストレスチェックの導入をご検討の方へ
ストレスチェックは、ただ実施するだけでなく、職場改善につなげることが重要です。
とはいえ、「何から始めればいいか分からない」「形だけの実施になっている」という声もよく耳にします。
弊社では、制度に準拠した実施はもちろん、結果を活かす運用までサポートしています。
初めての企業様でも安心して導入いただけるよう、シンプルで負担の少ない仕組みをご用意しています。
「義務対応」で終わらせず、働きやすい職場づくりにつなげたい方は、ぜひご相談ください。
▶ 詳しくはこちら