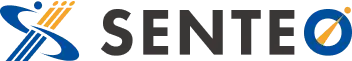営業職の離職率が高い!その要因とエンゲージメントを高める方法とは

目次
「営業の離職率が高くて困っている…」
そう感じたことのある経営者や人事担当者は、決して少なくないはずです。営業職は企業の売上を担う要のポジションでありながら、常に離職率の高さが課題として挙がっています。
事実、営業職は全職種の中でも特に離職率が高い職種の一つとされており、人材の定着が企業成長の大きな足かせになっているのが現実です。
毎年の採用・育成にかかるコストがかさむ一方で、ようやく戦力となった人材が辞めてしまう。
この悪循環は、営業成果の低下だけでなく、組織のモチベーションや顧客対応の品質の低下にもつながりかねません。
では、なぜ営業職はこれほどまでに辞めやすいのか?
そして、どうすれば「辞めない営業組織」をつくることができるのか?
本記事では、「営業 離職率」が高くなる要因を明らかにしながら、エンゲージメントを高め、離職を防ぐための具体策を実例を交えて解説していきます。採用に頼らない“強い営業組織”をつくるためのヒントがきっと見つかるはずです。
第1章:なぜ営業職は離職率が高いのか?主な原因とは
営業職は、企業の売上に直結する重要なポジションです。しかしその一方で、他職種と比べても離職率が高いことが多くの企業で課題となっています。その背景には、以下のような要因が複合的に存在しています。
1. 成果主義による強いプレッシャー
営業職は、常に売上目標やKPIといった「数字」で評価される職種です。
成果が上がらなければ評価は下がり、プレッシャーに押しつぶされてしまうこともあります。特に若手社員にとっては、このストレスが離職の大きな要因となります。
2. マネジメントの未熟さ
プレイヤーとして優秀だった人がそのまま管理職になり、育成やサポートの経験が乏しいままチームを任されているケースは少なくありません。適切なフィードバックやフォローが不足し、部下は孤独や不安を抱えたまま働くことになります。
3. 顧客対応による精神的ストレス
営業は社内外問わず多くの人と関わる仕事です。
特にクレーム対応や無理な要望への調整などは、感情労働として蓄積されます。自分の裁量ではどうにもならない案件に疲弊し、やがてモチベーションを失っていきます。
4. キャリアパスが見えにくい
営業で成果を出し続けることは求められても、その先のキャリアが不明瞭な場合があります。昇進・異動・スキルの応用先といった「未来の自分像」が描けないことが、離職を考えるきっかけになります。
5. 育成制度の不備
中小企業を中心に、新人を即戦力として現場に送り出す傾向があります。体系的な研修やロールプレイなどの教育機会が不足しており、早期に「自分には向いていない」と感じて辞めてしまうケースも少なくありません。
このように、営業職の離職は個人の性格やスキルの問題ではなく、制度や支援体制の未整備、そしてマネジメントのあり方に起因するケースが多いのが実情です。
次章では、こうした環境で「エンゲージメント」がどのように低下していくのか、さらに深掘りしていきます。
第2章:営業職のエンゲージメントが低下する職場の特徴
営業職の離職率を下げるには、「エンゲージメントの維持・向上」が欠かせません。そもそもエンゲージメントとは、従業員が仕事や職場に対して持つ愛着や貢献意欲のことを指します。
エンゲージメントが高い社員は、困難な状況でも粘り強く成果を出し、職場への帰属意識も強くなります。一方で、エンゲージメントが低下すれば、日々の業務に意味を見いだせなくなり、離職のリスクが急上昇します。
では、営業職においてエンゲージメントが下がりやすい職場には、どのような特徴があるのでしょうか。
1. 評価や成果に対して納得感がない
売上数字が評価の大部分を占める環境では、「頑張っても報われない」「正当に見てもらえていない」といった不満が生じがちです。
行動プロセスや貢献度を見てもらえないと、やがて努力する意味を見失います。
2. 成果が出ないと孤立する空気がある
数字が振るわない社員に対して、冷たい態度や無関心が向けられる職場では、メンバー同士の信頼関係が育ちません。
失敗を共有しにくくなり、助けを求めること=弱さとされる風土は、エンゲージメントの低下を招きます。

3. 上司とのコミュニケーションが形式的
1on1ミーティングがあっても、事務的な進捗確認だけで終わっていませんか?
業績以外の悩みや気持ちを話せない関係性では、上司の存在がむしろプレッシャーになりがちです。
4. 達成感や称賛の機会が少ない
目標に届かなければ評価されず、達成しても「当然」とされてしまうと、社員はやる気を失います。
とくにプロセスや工夫を評価しない職場では、挑戦意欲が生まれにくくなります。
5. チーム内での目的意識が共有されていない
「何のためにこの提案をしているのか」「なぜ今この商品を推しているのか」など、背景や狙いが伝わっていないと、業務がただの作業になってしまいます。
目的が見えない仕事に人は熱意を持ちづらく、やがて惰性で働くようになります。
こうした要素が重なると、社員は心の中で「もう頑張らなくていいか」と感じるようになり、静かに離職を考え始めます。
離職は突然起こるように見えて、実は日々のエンゲージメントの低下が積み重なった結果なのです。
第3章:営業職の離職を防ぐために企業ができること
営業職の離職を減らすためには、単に「辞めさせない」仕組みを整えるだけでなく、社員が自ら定着したくなる職場環境をつくることが重要です。そのためには、マネジメント、制度、教育体制といった多方面での見直しが欠かせません。
以下に、企業が実践すべき対策を紹介します。
1. 適正な目標設定と公正な評価制度の構築
ノルマの水準が高すぎる、変動が大きいと不信感が生まれる
社員のスキルや経験に応じた現実的な目標設定が必要
定量評価だけでなく、プロセス・行動・姿勢も評価項目に含める
2. 定期的な1on1とフォロー面談の実施
月1回でも良いので、業績以外の話もできる時間を設ける
上司が部下のモチベーションや心理状態を把握する機会になる
離職の予兆を早期にキャッチできる
3. 報酬制度の多様化と柔軟性の導入
成果給だけでなく、努力や成長プロセスを評価する報酬要素を加える
チーム成果を還元する「チームインセンティブ」なども有効
お金以外の報酬(表彰制度、社内報での紹介など)も意識する
4. 営業に特化した教育・研修の強化
商品知識だけでなく、提案力やヒアリングスキルなどの本質的な力を育てる研修を実施
ロールプレイやOJTだけに依存せず、外部講師の活用も視野に
成長実感を持たせることで、仕事にやりがいを感じやすくなる
5. キャリア支援と社内異動の選択肢を示す
営業以外の職種にチャレンジできる機会があると、将来への安心感が生まれる
「ずっと営業だけ」という縛りがあると、離職以外に選択肢がなくなる
キャリア相談の機会を設け、個人の希望や強みに寄り添った配置を行う
これらの施策をすぐにすべて整えるのは難しいかもしれません。ですが、「人が辞める理由を減らす」のではなく、「人が続けたいと思える要素を増やす」という発想が、離職防止の鍵を握っています。
第4章:エンゲージメントを高める仕組みと実践例
営業職の離職率を下げるうえで、「辞めない理由」をつくるだけでは不十分です。むしろ重要なのは、「ここで働き続けたい」と思わせる組織づくりです。その中核を担うのが、従業員のエンゲージメントです。
エンゲージメントを高める取り組みは、必ずしも大規模な制度改革である必要はありません。日々のコミュニケーションや仕組みの見直しによって、営業職の意欲と定着率は着実に向上していきます。
以下に、具体的な施策を紹介します。
1. 心理的安全性のある職場環境を整える
「失敗しても咎められない」「質問や相談がしやすい」空気をつくる
上司が部下に対してリアクションを返す習慣を持つ
叱責よりも承認を優先し、安心して挑戦できる土壌を育む
2. チーム内コミュニケーションの活性化
朝礼での雑談、ペア営業、社内勉強会など、つながりを感じられる機会を意識的に増やす
オンライン環境でも「雑談タイム」「感謝を伝える場」などを設ける
孤立しない仕組みが、結果的に離職防止につながる
3. プロセスや努力を見える化・称賛する
目標未達でも「商談数」「提案書の質」「改善案の実行」などを評価
社内チャットや朝礼で、良い取り組みを共有する文化をつくる
成果に至るまでの道のりを認めることで、自己効力感が高まる
4. 定期的なフィードバックの仕組みを整備する
上司との1on1に加え、社内アンケートやパルスサーベイを活用
日常的な声を拾うことで、表面化しにくい不満や課題が見える
得られた声は、施策に反映することで信頼感が生まれる
5. 社外相談窓口を設置し、メンタル面のフォローを強化
「会社に直接は言いにくい悩み」を外部に相談できる体制があると安心感が生まれる
問題が深刻化する前に対応でき、早期離職の予防にも効果的
利用者の傾向やテーマを集計し、職場改善にも活かせる

エンゲージメントは、個人の努力だけで高められるものではありません。企業側の「関心」と「仕組み」があってこそ、社員は組織に対して信頼と誇りを持つようになります。
まとめ
営業職の離職率が高い背景には、成果主義のプレッシャー、マネジメントの質、キャリアの不透明さ、育成体制の不足といった、複数の要因が複雑に絡んでいます。個人の資質に帰属させるのではなく、職場や制度の構造的な課題として捉えることが重要です。
また、離職は突発的に起きるのではなく、日々のエンゲージメントの低下が積み重なった結果として現れます。社員が孤立し、評価されず、将来が見えない状態に陥ると、自然と心が離れていきます。
離職率の改善には、「辞めない仕組み」を整えるだけでなく、「続けたいと思える環境」をつくることが欠かせません。そのためには、上司との関係性、組織文化、評価のあり方など、あらゆる接点でエンゲージメントを高めていく視点が必要です。
営業職の離職に悩む企業は、まずは現場の声を丁寧に拾い上げ、改善に向けた一歩を踏み出すことが求められています。仕組みと信頼を両輪で動かすことで、営業組織は確実に変わっていきます。
営業職の離職率にお悩みの企業様へ。
弊社では、社員アンケートやストレスチェック、社外相談窓口などを通じて、エンゲージメントを可視化し、課題に応じた改善策をご提案しています。
現場の声から、離職を防ぐ職場づくりをはじめませんか?
▶ 詳しくはこちらをご覧ください。