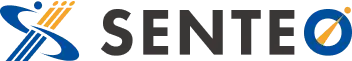【精神科医監修】メンタルヘルス対策の具体例まとめ。効果的な方法をシーン別に紹介

目次
1. はじめに|メンタルヘルス対策は“具体例”が鍵
職場でのメンタルヘルス対策は、今や企業の規模や業種を問わず求められる重要なテーマです。働き方の多様化や人手不足による負担増により、心の不調を抱える従業員は年々増加傾向にあります。実際に、厚生労働省の調査でも、従業員の約6割が仕事にストレスを感じているという結果が出ており、企業にとっては放置できない課題となっています。
とはいえ、「メンタルヘルス対策が大事なのは分かるが、何から始めればいいか分からない」「実際にどんなことをすれば効果があるのか知りたい」といった声も多く聞かれます。制度づくりや面談体制の整備など、取り組むべきことは多いものの、実際の現場で“使える具体例”がないと対策は形骸化しがちです。
そこで本記事では、精神科医の監修のもと、職場で実践できるメンタルヘルス対策の具体例をシーン別に整理してご紹介します。日常業務での予防策から、不調の兆候への対応、復職支援まで、それぞれの場面で効果的な方法をわかりやすく解説します。自社の取り組みを一歩前に進めるヒントとして、ぜひ参考にしてください。
2. メンタルヘルス対策の基本とは
メンタルヘルス対策と一口に言っても、その目的や手法は多岐にわたります。企業が対策に取り組む理由はさまざまですが、共通して言えるのは「従業員の心の健康を守ることで、組織全体の生産性や持続可能性を高めること」です。メンタルの不調は業務効率の低下や休職・離職といった事態を引き起こす要因となるため、早期の予防と継続的な支援が求められます。
厚生労働省では、メンタルヘルス対策を3つの段階に分けて整理しています。
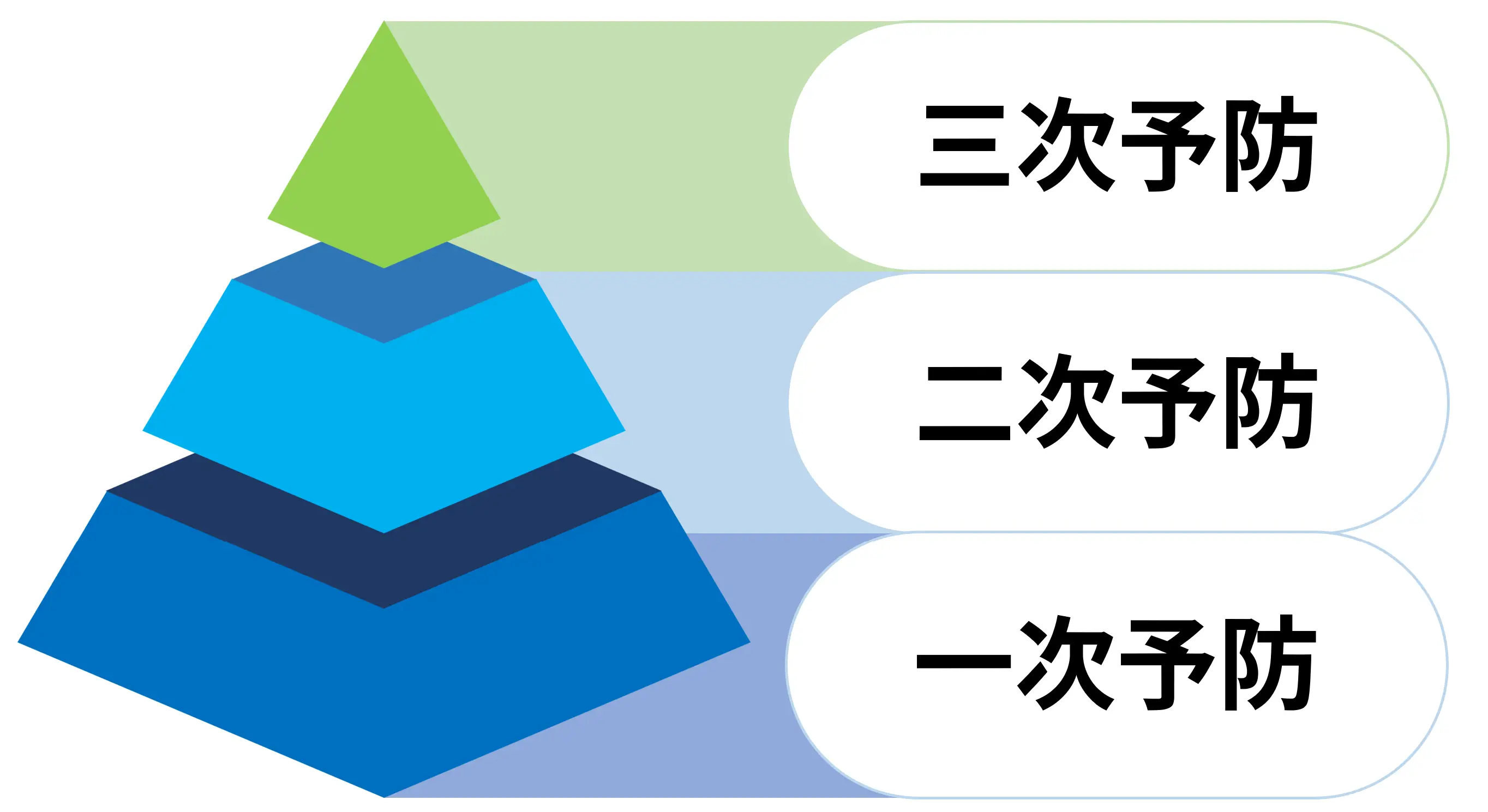
一次予防:不調を未然に防ぐ取り組み
→例:ストレスチェック、職場環境改善、教育・研修、相談体制の整備二次予防:不調の早期発見・早期対応
→例:上司・同僚の気づき、産業医面談、EAP(外部支援)の活用三次予防:回復支援と再発防止
→例:復職支援プログラム、リワーク支援、職場復帰後のフォローアップ
このように、メンタルヘルス対策は単発で完結するものではなく、日常的に積み上げていくプロセスが重要です。たとえば、ストレスチェックを毎年実施している企業も少なくありませんが、実施後に分析や改善アクションにつながっていなければ、十分な効果は見込めません。
また、単に制度や仕組みを整備するだけでなく、それが「従業員にとって実感できる支援」になっているかを確認する視点も欠かせません。対策の有無ではなく、実効性があるかどうかが問われる時代に入ってきているのです。
加えて、メンタルヘルス対策は人事部門だけの仕事ではなく、管理職をはじめとする現場の理解と協力も不可欠です。上司が部下の変化に気づき、早めに声をかけられる環境があるか、あるいは復職時にチーム全体で支える体制ができているかどうか――こうした“職場単位の支援力”が、最終的な対策の成果に大きく影響します。
次章では、こうした基本方針をふまえたうえで、シーンごとに分けた「具体的な対策例」をご紹介します。現場で実践しやすく、効果を感じやすいアプローチを中心に取り上げていきます。
3. シーン別に見るメンタルヘルス対策の具体例
ここからは、職場で実際に活用できるメンタルヘルス対策を、4つのシーンに分けてご紹介します。導入のしやすさや効果の出やすさを意識しながら、現場で「今すぐ使える」内容を中心にまとめました。
3-1. 日常業務での予防策(一次予防)
まず重要なのが、不調を未然に防ぐための取り組みです。代表的な例としては、ストレスチェックの実施が挙げられます。ただし、チェックを行うだけで終わるのではなく、集団分析結果を活用して職場環境の改善につなげることが求められます。
また、定期的な1on1面談や社外相談窓口(第三者による外部カウンセリング窓口)を設置することで、従業員が気軽に悩みを吐き出せる環境を整えることも予防につながります。特に、外部窓口は「社内では話しにくい」声を拾える仕組みとして有効です。

研修の実施も効果的です。たとえば、新入社員にはセルフケアの基本、管理職にはラインケアの知識や部下との接し方など、対象者に応じた内容で実施するとより実践的になります。
3-2. 不調の兆候が見えたときの対応(二次予防)
次に、不調のサインが見えた段階での対応です。従業員が急に無口になったり、遅刻やミスが増えたりといった行動変化は、不調の前兆であることがあります。
この段階で大切なのは、「早めに声をかけること」と「話を聞くスキル」です。管理職向けには“傾聴”や“共感”の姿勢を学ぶ面談トレーニングの導入が効果的です。
また、社内で対応が難しい場合には、産業医面談やEAP(Employee Assistance Program)など外部専門家の力を借りるのも一つの方法です。自社だけで抱え込まず、早い段階で外部につなぐ体制を整えておくことで、症状の悪化や長期休職を防ぐことができます。
3-3. 休職者への対応・復職支援(三次予防)
実際に休職者が出た場合、復職支援の体制も重要です。たとえば、「復職判定の基準が曖昧」「復職後のフォローが不十分」というケースでは、再休職のリスクが高くなります。
そのため、医療機関と連携した復職判定会議や、段階的な復職支援プログラムの導入が有効です。具体的には、復職初期は短時間勤務から始め、業務量や責任を段階的に戻していくステップが推奨されます。
また、復職後も上司や同僚との定期的なフォロー面談を継続し、孤立させないよう配慮することが再発防止につながります。
3-4. 管理職・経営層が知っておくべき対策
メンタルヘルス対策は現場任せにするのではなく、管理職や経営層が率先して関わることが重要です。たとえば、上司自身がストレスを抱えていたり、部下のメンタル不調を「気合いで乗り越えろ」と捉えていたりすると、対策の浸透は難しくなります。
そこで、管理職向けのセルフケア研修や、経営層を対象としたメンタルヘルスの重要性を学ぶセミナーの開催も効果的です。
加えて、ハラスメント防止の啓発や、心理的安全性の高い職場文化づくりも、長期的な対策として欠かせません。
4. メンタルヘルス対策の効果を高めるコツ
せっかくメンタルヘルス対策を導入しても、「制度があるだけ」で終わってしまっては意味がありません。対策を“効果の出る仕組み”に育てていくには、以下のようなポイントを押さえることが大切です。
■ データを活かした改善サイクルを作る
ストレスチェックやアンケート結果は「やりっぱなし」にせず、活用することが重要です。
特に以下のような流れが効果的です。
実施:ストレスチェック・アンケートを定期的に実施
分析:部署・職種ごとの傾向を把握(集団分析)
対策:数値に基づいた改善アクションを企画
評価:改善後の変化を再度チェック(PDCAの循環)
データに基づいた対策は、属人的な判断や感覚ではなく、客観的な根拠に基づいているため、従業員や管理職の「納得感」が得やすくなります。
■ 現場の「声」を拾える仕組みを設ける
管理職や人事に届かない「本音」は、別のチャネルで吸い上げる必要があります。
以下のような仕組みが有効です。
匿名アンケート(自由記述欄を設ける)
社外目安箱(第三者が間に入り、企業へフィードバック)
外部相談窓口(守秘義務を担保し、安心して相談できる体制)
匿名でのアンケートや社外目安箱を通じて集まる声は、「まだ問題化していない予兆」を見つける貴重な手がかりになります。

■ 効果の「見える化」で信頼性を高める
導入した施策がどれだけ効果を生んだかを示すことも重要です。
休職率や離職率の変化
従業員満足度の推移
対策実施後のエンゲージメントスコア
「やって終わり」にしないためには、施策の結果を数値で可視化し、関係者に共有することが不可欠です。
■ 経営層の関与がカギ
現場任せでは対策は浸透しません。経営層が率先して発信・行動することで、従業員の安心感につながります。
経営メッセージにメンタルヘルスを盛り込む
管理職研修・制度改革への投資を惜しまない
社内報や会議で定期的に取り上げる
トップが真剣に取り組んでいるという姿勢が伝われば、従業員の信頼を高め、全社的な意識改革の起点となります。
まとめ|現場で使えるメンタルヘルス対策から始めよう
メンタルヘルス対策は、特別なことをしなければならないと思われがちですが、実は「現場でできる小さな工夫」の積み重ねこそが、不調の予防や早期対応につながります。本記事では、一次・二次・三次予防という3つの段階に沿って、現場で実践できる対策を具体的にご紹介しました。
たとえば、ストレスチェックや1on1面談の実施、社外相談窓口の整備といった一次予防の取り組みは、すでに多くの企業が取り入れやすい施策です。そこに「データを活用する視点」「従業員の声を拾う仕組み」「効果の見える化」を加えることで、単なる“制度”から“実効性のある支援”へと進化させることができます。
また、不調のサインに気づいたときに適切に対応できるよう、上司や管理職の面談スキルや共感的なコミュニケーション力を育てる研修も重要です。復職支援においては、段階的な職場復帰や周囲のサポート体制の整備が再発防止のカギになります。
そして何より、こうした取り組みを現場に任せきりにせず、経営層が積極的に関与し「組織として取り組む姿勢」を示すことが、従業員の安心と信頼を生み出します。トップダウンとボトムアップの両面からアプローチすることで、社内全体に「心の健康を大切にする文化」が根づいていくのです。

メンタルヘルス対策に“正解”はありません。大切なのは、自社の状況に応じて「できるところから始め、少しずつ改善を重ねていくこと」です。課題が見えていない場合には、匿名アンケートや外部の支援サービスを活用することで、本質的な課題に近づくことができます。
精神科医や専門家のサポートを受けながら、自社のメンタルヘルス対策を次のステップへと進めていきましょう。
まずは、自社に合った取り組みを見つけることから始めてみませんか?
弊社では、精神科医監修のもと、ストレスチェック・社外相談窓口・職場アンケートなど、企業の状況に応じたサポートをご提供しています。
お悩みやご相談がある方は、ぜひ下記よりお気軽にお問い合わせください。
▶ お問い合わせはこちら