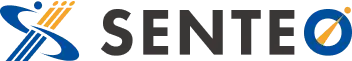ストレスチェックは意味ないって本当?十分な効果を得るためのポイントと活用事例
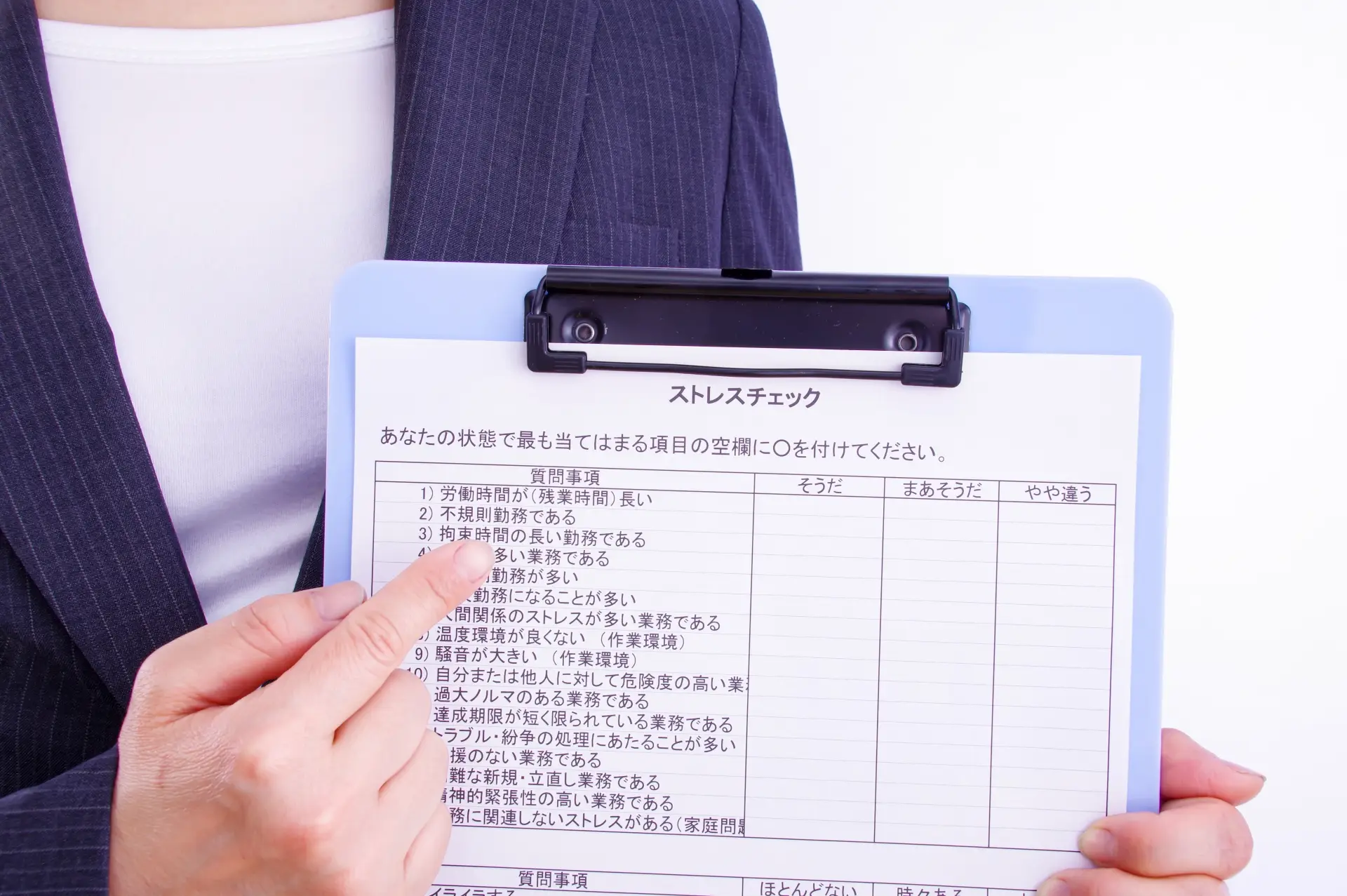
目次
1. 「ストレスチェックは意味ない」と言われる理由
「ストレスチェックって、正直意味あるの?」「毎年やってるけど、何か変わった感じがしない」――そんな声を、現場の従業員や人事担当者から耳にすることは少なくありません。2015年の法改正により、従業員50人以上の事業場で義務化されたストレスチェック制度。今や多くの企業で実施されていますが、その効果については疑問視する声も根強くあります。
では、なぜ「意味がない」といった否定的な評価が生まれるのでしょうか。その背景には、多くの企業で「チェックして終わり」になってしまっている現実があります。
実際に挙げられる問題点としては、次のようなものがあります。
フィードバックがない:結果を出しても、その後に何のアクションも起こされない
組織改善につながっていない:個人のストレス状況を測るだけで終わっている
内容が形骸化している:毎年同じ質問、同じ対応で従業員に飽きられている
相談体制がない・信頼されていない:相談しても変わらないという諦めがある
中でも特に多いのが、「結果を見ても何も変わらない」という声です。部署ごとの傾向が明らかになっても、それをもとに改善アクションが実施されなければ、従業員は失望し、制度に対する関心や信頼を失ってしまいます。また、相談窓口があったとしても、「相談しても無駄」「評価に悪影響があるかもしれない」と思われてしまえば、誰も活用しなくなります。
さらに、ストレスチェックが“年中行事”のように捉えられてしまっているケースもあります。実施時期は毎年同じ、設問も変化がなく、回答も義務的に済ませるだけ。企業側も「義務を果たした」という形式的な運用に終始していては、本来の目的である職場改善にはつながりません。
つまり、「ストレスチェックは意味ない」とされるのは、制度そのものに問題があるのではなく、その活用方法と運用姿勢に課題があるということです。効果を引き出すには、「やること」自体ではなく、「どう活かすか」が何より重要なのです。
2. ストレスチェックの本来の目的と役割
ストレスチェックは、単に従業員のストレス状態を確認するだけの制度ではありません。その本来の目的は、大きく2つに分けられます。
1つ目は、従業員本人が自分のストレス状態に気づき、早めの対処につなげること。メンタルヘルス不調は、症状が表面化するまでに時間がかかることが多く、自覚が遅れると回復にも時間がかかります。ストレスチェックは、早期の気づきとセルフケアの促進を目的としています。
2つ目は、職場環境全体の改善です。これは多くの企業で見落とされがちですが、実はこの部分こそが、制度の核といえる部分です。ストレスチェックは、個人の状態だけでなく、部署単位・全社単位で「どこにどんなストレス傾向があるか」「どのような職場要因が問題か」を可視化できる仕組みになっています。ここで得られた集団分析の結果を基に、職場環境の改善や業務設計の見直しを行うことが、制度の本来の狙いなのです。
ストレスチェック制度は、次のような流れで活用されることが想定されています。
- 従業員に対するストレスチェックの実施
- 結果を本人にフィードバック(希望者には産業医との面談を実施)
- 部署・組織単位での集団分析を実施
- 分析結果をもとに、具体的な職場改善アクションを実施
このように、チェックの結果を活かし、職場全体の働きやすさや安全性を高めるところまでが、制度に求められている役割です。
しかし現実には、多くの企業が「チェックで終わる」ステップ2で止まってしまっており、集団分析も活用されないまま保管されているケースが散見されます。あるいは、分析はしていても、その後の改善施策が曖昧だったり、現場に共有されていなかったりすることで、従業員にとって「意味のあるもの」として認識されなくなってしまうのです。
ストレスチェックを単なる義務と捉えるのではなく、「組織をより良くするためのツール」として位置づけ直すことが、制度を活かす第一歩となります。効果を引き出すには、“チェック”そのものよりも、“その後”にこそ、本当の価値があるのです。

3. ストレスチェックを「意味あるもの」にするための3つのポイント
ストレスチェックが「意味ない」と感じられてしまうのは、制度の内容よりも、活用の仕方に原因があります。では、どうすれば制度を実効性あるものにできるのでしょうか。ここでは、効果を最大限に引き出すための3つのポイントをご紹介します。
ポイント1:集団分析を活かした職場改善アクション
最も重要なのは、部署ごとの傾向を把握し、職場改善につなげることです。たとえば、集団分析の結果から以下のような傾向が見えてくることがあります。
業務量過多で「仕事の量」にストレスを感じている部署
人間関係に課題があり、「対人関係」に強いストレスを抱えるチーム
「上司からの支援」や「職場の一体感」が欠けていると感じている職場
このようなデータを放置せず、職場環境の改善につなげることが求められます。具体的には、業務の再分担やマネジメント研修、1on1ミーティングの導入など、部署ごとの課題に応じた対策が有効です。単なる報告資料で終わらせず、行動に落とし込むことが信頼回復への第一歩となります。
ポイント2:信頼される相談・面談体制の整備
高ストレス者に対する面談勧奨も、制度の大きな柱です。しかし「面談を受けても何も変わらない」「不利益があるかも」と感じられてしまえば、誰も手を挙げません。面談体制を機能させるためには、
面談の内容や目的、流れを事前に説明し、不安を払拭する
面談を担当する産業医やカウンセラーのプロフィールを公開する
完全にプライバシーが守られることを明記する
必要に応じて、社外相談窓口の導入も検討する
など、相談の“しやすさ”と“安心感”を担保する仕組みが欠かせません。
ポイント3:経営層・管理職の巻き込み
現場だけでストレスチェックを活かすには限界があります。組織全体で改善に取り組むには、経営層や管理職の理解と行動が必要不可欠です。具体的には、
経営トップから「ストレスチェックを組織改善に活かす」と明言する
管理職に対して、分析結果の見方や活用方法の研修を行う
管理職自身のストレス傾向も把握し、サポート体制を設ける
など、組織の上層部を巻き込んだ体制が、現場の本気度を支えます。従業員は意外と冷静に、会社の本気度を見ています。「やっている感」ではなく「本当に変える気があるかどうか」が、信頼やエンゲージメントに直結するのです。

4. 実際の活用事例:意味あるストレスチェックとは?
ストレスチェックを形式だけで終わらせず、職場改善の起点として有効に活用している企業も確かに存在します。ここでは、厚生労働省や健康経営優良法人の報告をもとに、実在事例を元にした2つの取り組みをご紹介します(企業が特定されないよう情報は一部加工しています)。
事例1:従業員200名規模の企業の取り組み
この企業では、数年間にわたりストレスチェックを実施していたものの、結果は集計して終わり。従業員に対するフィードバックもなければ、組織改善につながるアクションもありませんでした。当然ながら、現場の反応は「やっても意味がない」と冷ややかで、制度が形骸化していたのです。
転機となったのは、外部の専門機関と連携して集団分析をベースにした改善プロジェクトを立ち上げたことでした。分析の結果、特定の部署で「裁量が少ない」「上司との関係が希薄」といったストレス要因が明らかになり、以下のような施策が実施されました。
管理職に対する傾聴スキルやフィードバック研修の実施
業務プロセスの見直しによる裁量権の付与
定例の1on1ミーティングの導入
これにより、従業員の声が徐々に現場に届くようになり、翌年には高ストレス者の割合が約半分に減少。社内アンケートでも「上司が話を聞いてくれるようになった」「働きやすくなった」といったポジティブな変化が見られるようになりました。
事例2:従業員100名未満の企業の取り組み
この企業では、ストレスチェックの集団分析において「職場の一体感の欠如」「対人関係でのストレスの高さ」といった傾向が特定部署で強く表れていました。そこで会社は、心理的安全性の向上に焦点を当て、以下の施策を導入しました。
部署を越えたプロジェクトチームの結成で交流機会を増加
社外の匿名相談窓口の開設
これらの取り組みにより、「職場の雰囲気が良い」と答えた社員の割合が30%以上増加。さらに、その年の離職者はゼロとなり、特に若手社員の定着率に大きな変化が見られました。
どちらの事例にも共通するのは、「ストレスチェックを受けた後、具体的なアクションを起こしたこと」です。結果を見て終わりにするのではなく、改善の材料として活用し、従業員と向き合ったからこそ、組織全体の信頼と活気が回復していきました。
5. まとめ:「ストレスチェックは意味ない」を終わらせるために
「ストレスチェックは意味ない」と言われる背景には、制度そのものの欠陥ではなく、活かし方の工夫と実行力の不足があることがわかります。実施するだけで満足してしまえば、従業員にとっては単なる“形式的な儀式”に見えてしまい、制度への信頼も、職場への期待も薄れていきます。
一方で、実際に改善に取り組んだ企業の事例を見れば、ストレスチェックには「職場の問題を見える化し、行動のきっかけを与える力」があることも明らかです。チェック後の集団分析を丁寧に行い、現場に即したアクションを起こすことで、信頼やエンゲージメントの向上、さらには離職率の改善につながることもあるのです。
重要なのは、以下のような視点です。
結果を「見て終わり」にせず、「何を変えるか」に踏み出すこと
従業員の声を聞き流さず、具体的な施策に結びつけること
経営層・管理職も巻き込み、全社的な改善ムードをつくること
制度を“本気で活かす”姿勢こそが、従業員の不信を払拭し、組織の変化を後押しします。
義務だからやる、ではなく、組織づくりの手段として取り組む――。この視点を持てるかどうかが、「意味ある」ストレスチェックになるかどうかの分かれ道です。

📌職場改善につながるストレスチェックを実現したい方へ
「形だけのストレスチェックでは終わらせたくない」
「本当に職場を変えるきっかけにしたい」
そうお考えの方に向けて、弊社ではストレスチェックの実施から集団分析、改善アクションの設計までをトータルで支援するサービスを提供しています。
さらに、外部相談窓口やカスタマイズ可能なフィードバックレポートなど、組織の実情に応じた柔軟な設計が可能です。
✔ 結果を「見て終わり」にしない
✔ 高ストレス者への対応に迷わない
✔ 現場が納得する改善プランを立てられる
そんな「意味あるストレスチェック」を導入したい方は、まずは以下のサービスページをご覧ください。