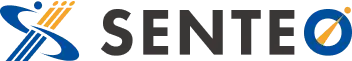管理職の不調が組織を壊す?経営・人事が知っておくべきメンタルヘルス対策
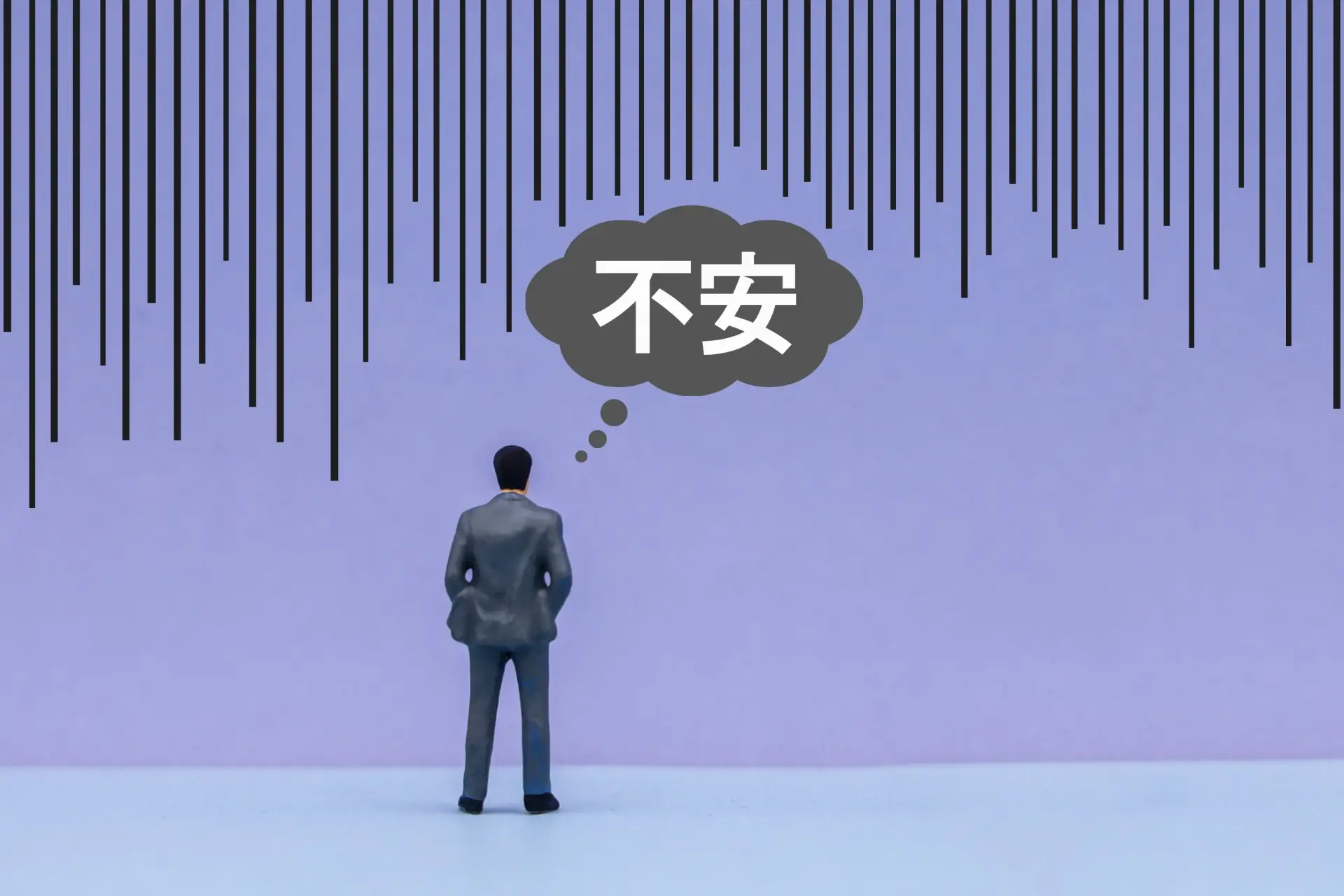
目次
1. なぜ今、管理職のメンタルヘルスが問題になるのか
これまでの「メンタルヘルス対策」は、主に一般社員を対象とした施策が中心でした。
しかし近年、「管理職自身の不調」が組織全体に深刻な影響を及ぼすリスクとして、注目され始めています。
管理職は、プレイヤーであると同時にマネージャーという二重の役割を担い、組織の方針を現場に落とし込む「橋渡し役」です。さらに、部下の不調にも気を配る必要があり、その中で自らがメンタル面で追い詰められてしまうと、以下のような悪循環が生まれます。

部下への適切なマネジメントができず、エンゲージメントが低下する
相談や報連相が滞り、心理的安全性が損なわれる
指示や判断にブレが生じ、現場の混乱・生産性の低下を招く
コミュニケーションのすれ違いが、ハラスメントと受け取られやすくなる
離職者の増加や、採用・教育にかかるコストの増大につながる
これらは、単なる一人の「不調」にとどまらず、組織全体のパフォーマンスや信頼に直結する重大な問題です。
さらに深刻なのは、こうした兆候が見逃されやすい点です。多くの管理職は、「弱音を吐いてはいけない」「頼られる存在でなければならない」という意識から、SOSを出すことすらできずに孤立しています。
このような企業文化が、不調の放置と悪化を常態化させる温床になっているのです。
では、なぜ管理職は、ここまでメンタル不調に陥りやすいのでしょうか?
2. 管理職はなぜメンタル不調に陥りやすいのか
管理職がメンタル不調に陥りやすい背景には、役割構造の複雑さと心理的な孤立があります。経営層や人事からは「頼れる存在」として信頼され、部下からは「助けてくれる存在」として期待される――。
その両方の期待に応えようとするほど、板挟みとなり、心身への負担が大きくなっていきます。
特に現代の管理職は、以下のようなストレス要因を日常的に抱えています。

管理職が抱える主なストレス要因
1. 上層部の意向と現場の実情のギャップに悩む
経営陣からは「業務効率化」「コスト削減」といった指示がトップダウンで求められる一方、現場では人手不足や属人化、長年の慣習が根強く残っており、改革には抵抗感があるのが実情です。
そのギャップを埋める“調整役”を任され、上層部からも現場からも不満の矢面に立たされ続けることが、管理職にとって大きな精神的負担となっています。
2. “成果”と“人間関係”の両立プレッシャー
「心理的安全性」「1on1」「共感型リーダーシップ」などが重視される一方で、管理職には相変わらず数値での成果も求められます。つまり、“優しいだけ”でも“結果だけ”でも評価されません。
部下への改善指導においても、「ハラスメントと思われないか」「モチベーションを下げないか」といった懸念から、言葉を選びすぎて本音が伝えられない――。
この伝え方のジレンマが、慢性的なストレスを引き起こします。
3. プレイングマネージャーとしての業務過多
人手不足や組織のスリム化が進む中、「管理職でありながら現場業務を担う」状況が常態化しています。日中は会議・部下対応・クレーム処理、夕方以降にようやく自分の仕事に着手。
気づけば20時を回り、資料を持ち帰って作業する日々。常に時間に追われる感覚が、ストレスを加速させます。
4. 誰にも相談できない孤独感
部下に弱音を吐けば「頼りない」と見られ、上司に相談すれば「任せたのに」と評価に響くかもしれない。同期には競争意識がある――。
こうした背景から、管理職は組織内で**“安全に相談できる相手”を持ちにくい立場**にあります。
本音を話せない状態が続くことで、孤独感や無力感が蓄積し、バーンアウト(燃え尽き症候群)に至るリスクも高まります。
5. 常に評価される立場
管理職は、自身のパフォーマンスだけでなく、部下の成果やチームの状態までもが評価の対象になります。「部下のモチベーションが低い」「離職率が高い」といった間接的な要素まで、自分の責任とされることも。
こうした状況では、「常に見られている」「失敗できない」という緊張感が常態化し、慢性的なストレス反応を引き起こします。
これらのストレスは、一つひとつは軽微に見えても、常に複数が重なっていること、そして「管理職なんだから我慢して当然」という価値観により、支援される機会を失っていることが問題です。
ある調査では、部下のメンタル不調への対応方法が「わからない」と答えた管理職は約7割にのぼります。自分自身の不調を自覚していても、「助けを求められない」と感じているケースも少なくありません。さらに、ハラスメントやトラブルが起きた際には、多くの場合、「管理職の指導不足」として処理されてしまう構図が存在します。これが、「何があっても自分の責任」と受け止める心理的重圧につながり、自己肯定感の低下を招くのです。
現代の職場では、「心理的安全性」や「感情労働」への理解と対応が求められていますが、実際に支援体制が整備されている企業はごく一部に限られます。
頑張る人ほど疲弊する構造。
これこそが、今、管理職のメンタルヘルス対策が急務とされている最大の理由なのです。
3. 企業事例に学ぶリスクと改善策
管理職のメンタル不調が企業に与える影響は、想像以上に広範囲に及びます。ここでは、具体的な事例をもとに、よくあるリスクと、その対応策から得られる学びをご紹介します。
■ ケース1:不調に気づけなかったことが組織の崩壊を招いた
ある企業では、複数の従業員が立て続けに休職し、その背景には管理職のメンタル不調があったことが後に判明しました。上司が常にピリピリしていた、部下の小さな不調に目を配る余裕がなかった、指示が二転三転する――。当初は「業務の忙しさのせい」と片づけられていましたが、実際にはその管理職が抱える慢性的なストレスが原因でした。
対策として行われたのは以下のような取り組みです:
- 管理職本人へのストレスチェックの実施と、結果のフィードバック
- 「管理職も相談してよい」というメッセージを全社的に発信
- チーム全体の雰囲気を可視化し、マネジメント負荷を検討材料に
こうした対応を通じて、管理職が自分の状態を客観視できるようになり、部下との関係性も少しずつ改善していきました。個人の不調が組織全体の課題であることが共有されたことが、再発防止につながったのです。
■ ケース2:「相談できない管理職」の孤立が招いた悪循環
別の企業では、「相談できない管理職」が孤立し、結果的に業務上のトラブルや離職を引き起こしていました。管理職自身は「部下に弱みを見せてはいけない」と思い込み、異変が起きても我慢し続ける日々。人事や上司からも声をかけられず、気づけばチーム内の空気も悪化していたという状況でした。
この問題を受けて、企業は次のような工夫を取り入れました:
- 管理職が匿名で利用できる外部相談窓口の整備
- 管理職同士で気軽に意見交換できる場の設定(例:ラウンドテーブル形式)
- 上司が部下(=管理職)と定期的に「業務以外」の対話をする場の設定
結果として、管理職が「誰かに話してもいい」と思える心理的な安全性が生まれ、問題が深刻化する前に表面化するようになりました。“孤独な立場”である管理職に、つながりを取り戻す支援が功を奏した例です。
■ ケース3:復職後の支援不足で再休職が続発
ある企業では、メンタル不調で休職した管理職が復職後すぐに再び不調となるケースが相次いでいました。業務への復帰が急すぎたり、チームの受け入れ体制が整っていなかったりすることで、管理職本人が「また迷惑をかけてしまうのでは」というプレッシャーを感じていたのです。
企業側では、以下のような対応策が講じられました:
- 復職プロセスを段階的に設計し、負荷のかからない業務から再開
- 管理職とその上司との間で、復帰後の期待値や配慮事項を明文化
- チームメンバーへの「受け入れ方」に関する研修や対話の機会を提供
このようなサポートにより、本人が安心して再スタートを切れる環境が整備され、再休職のリスクが大幅に減少しました。復職は「本人の努力だけで何とかなるもの」ではなく、組織の準備と姿勢が問われる課題だという認識が社内に広まりました。

これらの事例に共通するのは、管理職のメンタル不調は「個人の弱さ」ではなく、「組織の構造や支援の不備」に起因するという点です。そして、適切な支援体制と文化的なメッセージ発信があれば、多くの問題は未然に防ぐことができるということも示しています。
管理職は、組織の「要」であると同時に、最も「折れやすい場所」でもあります。
だからこそ、経営や人事が率先してケアの目を向けることが、強い組織を育てる第一歩なのです。
4. 経営・人事が実践すべきメンタルヘルス対策
管理職のメンタルヘルス対策は、単なる「従業員支援」の延長ではなく、組織戦略の一部として設計する必要がある時代に入っています。
管理職が健全な状態でいることは、部下のパフォーマンス、チームの心理的安全性、組織文化そのものに直結するからです。
では、経営や人事は具体的にどのような支援を講じればよいのでしょうか。ここでは、「継続性」「構造化」「組織全体の意識変革」という観点から、実践すべき対策を紹介します。
■ 1. 管理職向けストレスチェックと状態把握の“定点観測”
一般社員と同じストレスチェックだけでは、管理職特有のストレス要因は把握しきれません。たとえば、以下のような設問を含めると、より実態に迫ることができます。
- 「部下とのコミュニケーションに困難を感じることがある」
- 「意思決定の負担を重く感じている」
- 「自分の相談先が明確である」
また、結果は集計するだけでなく、面談やフィードバックの機会をセットにすることで“気づき”を生むことが大切です。継続的なモニタリングにより、組織として“兆候”に早期対応できる体制を築けます。
■ 2. 「相談できる管理職」ではなく「相談される管理職」を支える
管理職には「部下の相談に乗るスキル」が求められる一方で、自分自身が相談する側になる機会が極端に少ないのが現状です。これを是正するために有効な対策は以下の通りです。
- 外部EAPや社外相談窓口の設置(匿名性の確保がカギ)
- 管理職向けのコーチング・カウンセリングの定期提供
- 自主的に話せる“雑談的”な1on1の場づくり(評価と切り離す)
重要なのは、「管理職も支援の対象である」というメッセージを経営側が明示的に発信することです。
そうすることで、「話してもいい」「助けを求めても評価は下がらない」という安全感が生まれます。
■ 3. 管理職向けメンタルヘルス研修の質と目的を見直す
従来のメンタルヘルス研修は、「部下の変化に気づくための視点」や「ハラスメントにならない指導法」など、対部下向けの内容が中心でした。
これからはそれに加えて、以下のようなテーマも取り入れる必要があります。
- 自分のストレスサインの見つけ方
- 感情のマネジメントと切り替え法
- 上司や人事への相談ルートの理解
- “完璧主義”や“責任感過多”とどう向き合うか
これらを学ぶことで、管理職自身が「セルフケアの感覚」を持つようになり、不調を早期に察知・対処できる素地が整います。
また、研修を一度限りのイベントで終わらせず、振り返りや継続支援を組み合わせることが効果的です。
■ 4. 健康経営の中核に「管理職ケア」を組み込む
管理職のメンタルヘルス対策は、健康経営の実行力を高める中核的要素です。
企業としては、以下のような形で「制度としての位置づけ」を明確にすることが求められます。
- 健康経営方針に「管理職の心身支援」を明記
- エンゲージメント調査や離職分析に「管理職の関与状況」を反映
- 評価制度に「マネジメントの健全性」も組み込む
これにより、健康経営が単なるスローガンではなく、「現場のリアルに根ざした施策」として浸透していきます。
■ 5. トップダウンとボトムアップの両輪で文化を変える
最後に忘れてはならないのが、「メンタルヘルスは恥ではない」という企業文化の醸成です。
これは、経営層からのトップダウンの発信と、管理職・従業員によるボトムアップの取り組みがあって初めて定着します。
たとえば:
- 経営者自身が「自分もストレスを感じる」と発信する
- 社内報や勉強会で、メンタル面のセルフケア情報を日常的に共有
- 小さな成功事例を積極的に言語化し、社内で称賛する
こうした取り組みにより、「相談してもいい」「支え合うのが当たり前」という雰囲気が根付き、管理職が自然に助けを求められる職場が実現されていきます。

まとめ:管理職の“こころの健康”を守ることが、組織の持続可能性を高める
管理職の不調は、チームの混乱、生産性の低下、離職の増加、さらには企業全体の信頼失墜へと直結します。
それを未然に防ぐカギは、経営と人事が「管理職も支援すべき存在」と明確に認識し、制度と文化の両面で支えることにあります。
メンタルヘルス対策はもはや、特別な人だけのものではありません。
組織を動かすすべての人――とくに管理職にとっての「心の安全網」を整えることが、健全な組織の成長と維持には欠かせないのです。

📩貴社に合った管理職支援策をご提案しています
株式会社SENTEOでは、ストレスチェックや状態分析、外部相談窓口の導入支援などを通じて、メンタルヘルスを軸とした組織改善をご支援しています。
ご相談・お見積もりは無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。
▶ ご相談・お問い合わせはこちら
👉 お問い合わせフォームリンク