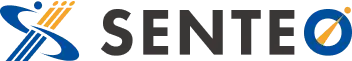メンタルヘルス不調者への対応方法|正しい接し方、再発防止策を解説
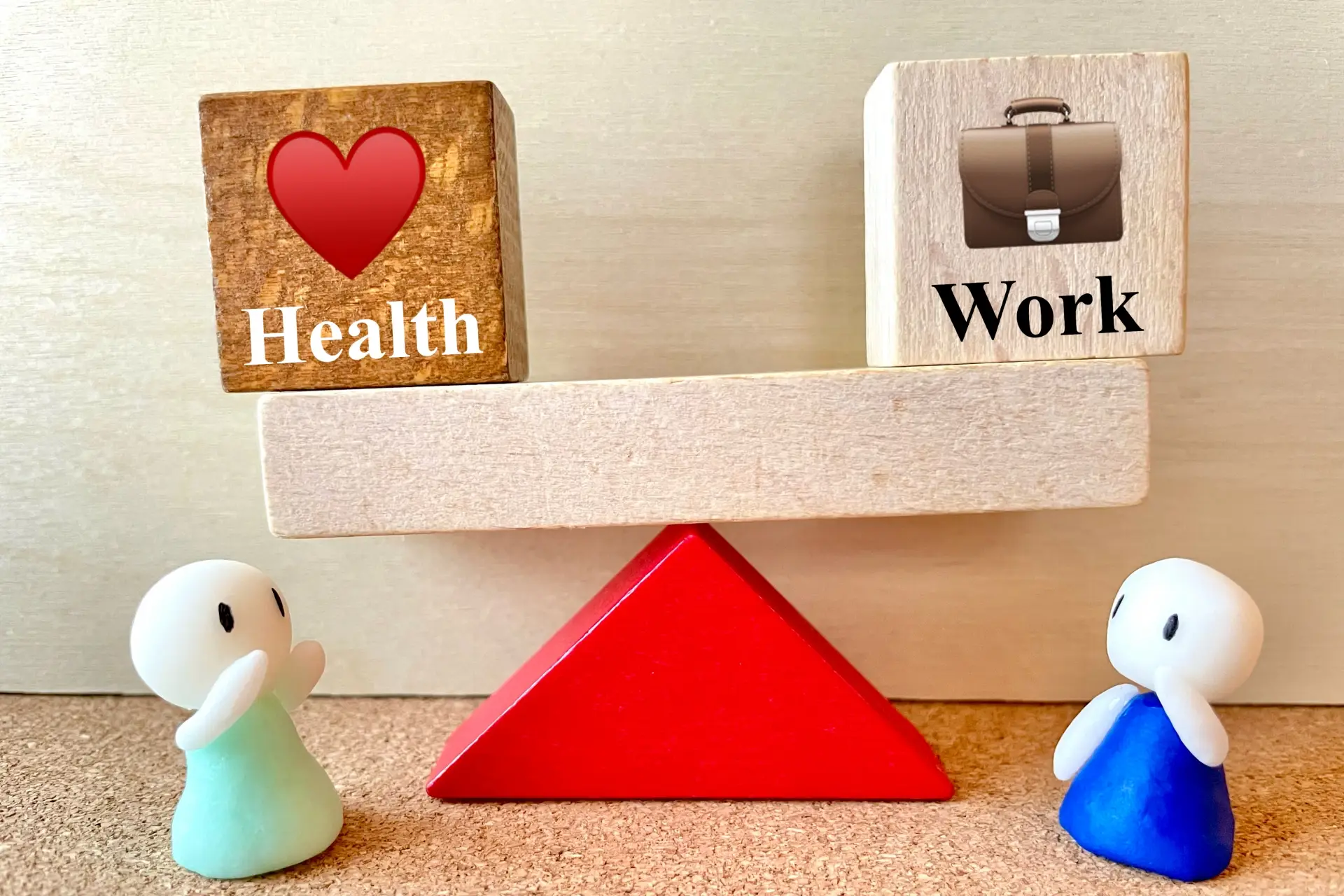
目次
職場で「最近遅刻が増えた」「なんとなく元気がない」といった変化を感じる従業員がいるとき、それはメンタルヘルス不調のサインかもしれません。
企業にとって、従業員のメンタルヘルス対応は「個人の問題」ではなく、組織の生産性・人材定着に関わる重要なテーマです。この記事では、不調の兆候をどう見抜き、どのように接し、復職・再発防止にどうつなげるかを、現場で役立つ観点から解説します。
1. メンタルヘルス不調者に見られるサインとは
メンタルヘルス不調は、初期段階では本人すら気づかないことがあります。だからこそ、周囲の小さな気づきが早期対応につながるのです。
特に注意すべき兆候は以下のようなものです。
遅刻・早退・欠勤が増える
仕事のミスが目立つようになる
表情が暗くなり、会話を避けるようになる
急に怒りっぽくなる、涙もろくなる
身だしなみや態度が以前と変わる
こうした変化が見られたら、「気のせいかも」で済ませず、一度しっかり向き合ってみる姿勢が求められます。
2. 初期対応の基本|正しい接し方とNG行動
不調が疑われる部下や同僚への「最初の声かけ」は、非常に重要なステップです。安心感を与える関わり方が、信頼関係の構築と回復のスタートになります。

適切な接し方のポイント
プライバシーが保たれる場所で話す
「最近、少し心配していて」とやわらかく伝える
話を否定せず、評価せずに聴く
共感的な姿勢で傾聴する
たとえば、「最近、ちょっと元気がないように見えて気になっています。何か困っていることがあれば話してくださいね」といった言葉は、相手に安心感を与えます。
一方で、次のような対応は避けなければなりません。
NGな対応例
「みんなだって大変だよ」といった励ましに見える否定
自分の経験談で相手の感情を押し流す
無理に原因や背景を探ろうとする
業務命令として一方的に関わる
大切なのは、「理解しようとしてくれている」と相手が感じられることです。それが、回復へのモチベーションや職場への信頼感につながります。
3. 不調者の職場復帰支援と再発防止策
メンタルヘルス不調からの回復には、休職期間だけでなく、復職後のフォロー体制が極めて重要です。
復職直後は、業務への不安や周囲の目に対する緊張感から再び不調が再燃しやすい時期。
だからこそ、回復の「出口」ではなく「スタート」としての支援体制が求められます。
復職支援のプロセスとポイント
- 主治医の診断書を確認
「就労可能」の明記があり、なおかつ具体的な配慮事項(短時間勤務や軽減業務など)にも目を通します。 - 産業医や人事との面談を実施
医学的な視点と会社側の就労環境をすり合わせ、現実的な働き方を設計します。 - 段階的な勤務再開(リワーク支援含む)
週数回からスタートし、徐々に勤務時間や業務量を増やす「スモールステップ」の考え方が基本です。 - 受け入れる職場側の理解醸成
配属先の上司や同僚にも一定の情報共有を行い、無理のないフォロー体制を整備します。
復職初期は、焦りや不安を抱えやすい時期です。業務内容や勤務時間をいきなり元に戻すのではなく、段階的に環境へ慣らしていくことが重要です。
再発防止のための具体策
復帰がゴールではなく、その後の「安定して働き続けられる」状態を維持するために、以下のような取り組みが有効です。
- 定期的なフォロー面談:月1回程度、人事・上司・産業医のいずれかが状態を確認し、不安の芽を早期に拾います。
- 業務内容や責任範囲の見直し:重要なのは「能力に合った役割」へのマッチング。配慮しすぎても本人の自信喪失につながるため、段階的に適正化します。
- 柔軟な働き方の導入:時短勤務、フレックス、リモートワークなどを状況に応じて一時的または長期的に導入します。
- 本人だけでなく周囲への教育・対話:復職者にだけ気を配るのではなく、チームとしてどう支えるかを全体で考えることが、真の再発防止になります。
再発を防ぐには、本人の「自己責任」にしない姿勢が必要です。
企業として“働きながら回復できる環境”を整備できるかが問われているといえるでしょう。
4. メンタルヘルス対応の体制づくりと職場全体での取り組み
メンタルヘルス不調への対応を、属人的なものにせず、組織として誰もが動ける「仕組み」と「制度」に落とし込むことが必要です。
一度でも不調者対応を経験した企業であれば、「あの時の判断は適切だったのか」「もっと早く動けなかったか」といった反省が残るものです。これを次につなげるためには、再現性のある体制づくりが不可欠です。

必要な制度・仕組みの整備ポイント
- 社内対応マニュアル・フローの明文化
たとえば「不調を訴えた社員に対しては、◯日以内に人事が面談を行う」「復職可否は産業医の意見をもとに決定」などのルールを設け、対応にブレをなくします。 - 社外相談窓口(EAP)を設置する
メンタル不調の背景にある家庭問題、人間関係、ハラスメントなどは社内では相談しづらい場合も。匿名で相談できる窓口を持つことで「抱え込みの防止」につながります。 - ストレスチェックを“活かす”運用へ
単なる実施で終わらず、部署ごとの集団分析を実施。高ストレス領域には重点的に対策を講じるなど、組織の健康課題を見える化・改善に結びつけます。 - 管理職向け研修の定期実施
メンタルヘルスに関する知識や対応スキルは、知っているようで実は曖昧な人が多いもの。初期対応を間違えることで悪化するケースも少なくありません。管理職は「気づきの窓口」として機能する存在だからこそ、研修が不可欠です。
これらの取り組みはすべて、「個人への対応」から「構造的な改善」へと進化させることを目的としています。属人的に頑張るのではなく、仕組みで支える。
これこそが、持続可能なメンタルヘルス対策です。
まとめ|「一人で抱え込まない」職場づくりを
メンタルヘルス対応は、本人の問題として片付けるのではなく、組織としてどう支えるかという視点で取り組むことが重要です。
小さな変化に気づく
早期に声をかける
適切に支援し、段階的に復帰を支える
再発を防ぐために環境を整える
これらの積み重ねが、従業員のエンゲージメントを高め、結果的に企業の生産性や採用力を強化することにもつながります。
職場のメンタルヘルス対応、プロの視点で見直してみませんか?
当社では、精神科産業医の監修のもと、現場で本当に使えるメンタルヘルス支援を提供しています。
たとえば、
ストレスチェックの効果的な活用支援
社外相談窓口(外部目安箱)の設置・運用サポート
職場改善アンケートの設計・実施・フィードバック分析
など、職場の実情や課題に応じた多角的な支援が可能です。
「離職率が気になる」「社員の本音が見えない」「何から始めればいいかわからない」
そんなお悩みがあれば、まずはお気軽にご相談ください。
▼ 詳しくはこちらから
👉 お問い合わせ