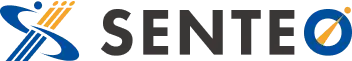職場のハラスメントをなくすには?原因と対策から学ぶ再発防止メソッド

目次
1. ハラスメントとは?職場での深刻な影響
ハラスメントの定義
ハラスメントとは、職場において他者に対して不適切な言動や行動を行い、精神的・身体的な苦痛を与えることを指します。職場環境を悪化させ、従業員の健康や生産性にも影響を及ぼすため、企業にとっても大きな問題となります。
パワーハラスメント(パワハラ)

パワーハラスメントとは、職場において地位や権力を利用して相手に精神的・身体的な苦痛を与える行為のことを指します。厚生労働省の定義によると、「業務の適正な範囲を超えた言動により、労働者の就業環境が害されるもの」がパワハラに該当します。
具体例
- 「お前は使えない!」と大声で怒鳴る(人格否定)
- 失敗を何度も責め続ける(過剰な叱責)
- 無理な業務を押しつけ、終わらなければ叱責する(過重労働の強要)
- 特定の社員だけ会議から排除する(差別・隔離)
被害者への影響
パワハラを受けた従業員は、ストレスや抑うつ状態に陥りやすく、最悪の場合、適応障害やうつ病につながることもあります。さらに、モチベーションの低下や休職・離職につながり、企業側にとっても大きな損失となります。
対策・回避策
- 上司が適切なフィードバックの仕方を学ぶ研修を実施
- ハラスメントの実態調査を行い、組織全体の意識改革を促す
- 相談窓口を設置し、匿名で相談できる体制を整える
セクシュアルハラスメント(セクハラ)

セクシュアルハラスメント(セクハラ)とは、性的な言動により相手に不快感を与えたり、職場環境を悪化させたりする行為のことを指します。厚生労働省では、セクハラを「対価型」と「環境型」に分類しています。
具体例
- 「女性は愛嬌が大事」などのジェンダー発言
- プライベートな恋愛や結婚の話を繰り返し聞く
- 飲み会で不必要に身体に触れる
- 性的な冗談を言う
被害者への影響
セクハラは特に職場の信頼関係を損なう原因となります。被害者が精神的ストレスを抱え、業務パフォーマンスが低下することが多く、場合によっては訴訟リスクも発生します。
対策・回避策
- 性的発言・行動の基準を明確にする社内ルールを設ける
- 従業員向けのセクハラ防止研修を実施する
- 被害者が安心して相談できる専門窓口を設置
モラルハラスメント(モラハラ)

モラルハラスメントとは、言葉や態度、態度によって相手を精神的に追い詰める「見えにくいハラスメント」です。パワハラやセクハラに比べて外から認識しづらく、被害者が長期間苦しむケースが多いのが特徴です。
具体例
- 陰口や無視を続ける(職場いじめ)
- 「どうせ無理だよね?」と能力を否定する発言をする
- メールやメモのみで指示を出し、対面でのコミュニケーションを拒否する
- わざと情報を共有せず、仕事ができないように仕向ける
被害者への影響
モラハラを受け続けると、被害者は**「自分が悪いのでは?」と自己否定に陥りやすくなります。さらに、長期間にわたるとうつ症状の悪化や退職**に追い込まれるケースも多く見られます。
対策・回避策
- 企業として「モラハラは問題行為」と明確に示す
- 上司・同僚との定期的な1on1ミーティングを実施し、心理的安全性を確保する
- 被害者が孤立しないよう、メンタルサポートを提供する
このように職場のハラスメントは、単なる人間関係のトラブルでは済まされません。これは、企業や従業員に深刻な影響を与える社会的な問題であり、放置すれば組織全体の健全性を損なう原因となります。次章からはハラスメントの原因について解説していきます。
2. 職場のハラスメントの原因とは?
1.上司・部下間の権力構造
職場では上下関係があるため、上司が部下に対して強く出やすい構造があります。適切なマネジメントができていないと、意図せずともパワハラに発展することがあります。
2.企業文化・風土の問題
長年続いている企業文化の中には、**「これくらい普通」「昔からこうだった」**という価値観が根付いていることがあります。
3.ストレスやコミュニケーション不足
職場のストレスが多いと、従業員同士のトラブルが増えます。また、テレワークの普及により、対面でのコミュニケーションが減少し、誤解が生じやすい環境になっていることも原因の一つです。

ハラスメントが見逃される理由
このようなハラスメントが職場で見逃される主な理由は、被害者が声を上げにくい環境があることです。上司や同僚からの報復を恐れ、また「我慢するのが普通」との意識が根強く、問題を表面化しづらいのです。さらに、管理職の認識不足や企業側の対応の甘さも要因です。「指導の一環」と誤認されるケースや、会社が問題を軽視して対策を怠ることで、ハラスメントは放置され、慢性化してしまいます。これを防ぐには、相談しやすい体制と明確な対策が必要です。
3. 職場のハラスメントをなくすには?効果的な対策と予防策
ハラスメントのない職場を作るには、企業が一方的にルールを定めるだけでは不十分です。従業員一人ひとりがハラスメントに対する理解を深め、安心して働ける環境を作ることが重要です。そのためには、経営層の明確な姿勢・従業員教育・相談体制の強化・職場環境の改善といった多面的なアプローチが必要になります。
ここでは、具体的な対策と予防策を詳しく解説します。
経営層のコミットメントと社内方針の明確化
1.経営層が率先してハラスメント対策に取り組む姿勢を示す

企業のトップが「ハラスメントは許されない」という明確なメッセージを発信することで、従業員の意識改革が進みます。特に、経営層自らがハラスメント防止研修に参加する、定期的にメッセージを発信するといった行動が効果的です。
2.社内規程や就業規則にハラスメント禁止を明記
「どのような行為がハラスメントに該当するのか」「加害者に対する処分はどうなるのか」といったルールを明文化し、社内に周知しましょう。具体的には、以下のような項目を盛り込むとよいでしょう。
- ハラスメントの定義と具体例(パワハラ・セクハラ・モラハラなど)
- 禁止事項(許容される行動との違いを明確に)
- 違反時の処分(懲戒処分の基準を設定)
- 相談・報告の手順(誰に、どのように報告するか)
従業員に対してこれらのルールを定期的に通知し、「知らなかった」「認識していなかった」という言い訳を防ぐことが重要です。
ハラスメント防止研修の実施と意識改革
1.研修を通じて正しい知識を浸透させる

ハラスメント対策の基本は、従業員一人ひとりが「何がハラスメントにあたるのか」を正しく理解することです。特に管理職は、指導との違いや適切な対応を学ぶ必要があります。
効果的な研修のポイントとして、以下の方法が挙げられます。
- ケーススタディ形式で学ぶ(実際の事例をもとにディスカッション)
- ロールプレイングを取り入れる(加害者・被害者・第三者の視点を体験)
- オンライン研修を活用する(忙しい従業員でも受講しやすい)
- 定期的に開催し、学習を定着させる(年1回以上)
特に管理職向けには、「適切な指導とハラスメントの境界線」を学ぶ研修が重要です。「強く叱責するとハラスメント?」「どこまでが許容範囲?」といった疑問を解決し、適切なマネジメントスキルを身につけてもらいましょう。
2.無意識のバイアスをなくすための教育も必要
「悪意がなければ問題ない」「昔はこれが普通だった」といった価値観がハラスメントを助長することがあります。そのため、無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)を認識し、適切な対応を取るための研修も重要です。
相談窓口の設置と迅速な対応
1.安心して相談できる窓口を設置する

被害を受けた従業員が声を上げやすいように、匿名で相談できる窓口を設置することが重要です。窓口の種類には、以下のようなものがあります。
- 社内相談窓口(人事部・コンプライアンス部門)
- 社外相談窓口(外部の専門機関や弁護士)
- オンライン匿名相談(専用フォーム・チャットツール)
社内窓口だけでは「加害者が上司の場合、相談しにくい」といった問題があるため、外部の窓口も用意することで、相談のハードルを下げることができます。
2.相談を受けたら迅速かつ公正に対応する
相談が寄せられた場合、企業は迅速かつ公正な対応をとる必要があります。具体的な対応手順は以下のとおりです。
- 被害者の話を丁寧にヒアリング(プライバシーを厳守)
- 関係者への事実確認(中立的な立場で調査)
- 必要に応じて加害者への指導・処分を実施
- 再発防止策を講じる(研修強化・職場環境の改善)
相談しても適切に対応されなければ、被害者の不信感が高まり、企業への信頼が損なわれるため、迅速な対応が求められます。
風通しの良い職場づくりとエンゲージメント向上
1.「心理的安全性」の高い職場を作る

ハラスメントが起こりにくい職場を作るには、従業員同士が互いを尊重し、安心して意見を言える環境を整えることが大切です。そのために、以下のような施策が効果的です。
- 定期的な1on1ミーティングを実施する(上司と部下の信頼関係を強化)
- 職場の雰囲気を見直す(管理職の対応や社風を改善)
- 従業員満足度調査を実施する(定期的なフィードバック収集)
従業員が「この職場なら安心して働ける」と感じられる環境を作ることで、ハラスメントの発生率を低減できます。
2.エンゲージメントを高め、働きやすい職場を作る
従業員が会社に対して愛着や働きがいを感じている場合、組織全体のモラルが向上し、ハラスメントの抑止力が働きます。そのためには、以下のような施策が有効です。
- 適切な評価制度を導入する(成果に見合った評価・報酬)
- 福利厚生を充実させる(ワークライフバランスの確保)
- メンタルヘルスケアを強化する(産業医・カウンセリングの活用)
職場のハラスメントを防ぐには、ルールを厳しくするだけでなく、従業員が心地よく働ける環境を整えることが不可欠です。
まとめ
- ハラスメントは企業・従業員に大きな影響を与える
- 企業の取り組みがカギ(研修・相談窓口・制度整備)
- 従業員同士の意識改革が必要

職場のハラスメントをなくすには、「企業の取り組み」「個人の意識」「制度の整備」が不可欠です。特に、継続的な対策を講じることで、ハラスメントのない健全な職場環境を実現できます。企業が主体的に取り組み、従業員一人ひとりが意識を持つことで、より良い職場づくりが可能になります。
職場のハラスメント対策にお悩みの方へ
ハラスメントをなくすには、社内での取り組みと同時に、専門的な知見を持つ外部パートナーとの連携も効果的です。
当社では、ハラスメント相談窓口の設置支援・制度設計のサポートを通じて、企業のハラスメント対策を支援しています。
「自社に合った対策を一緒に考えてほしい」「何から始めればいいかわからない」など、どんな段階でもお気軽にご相談ください。
→ お問い合わせはこちら